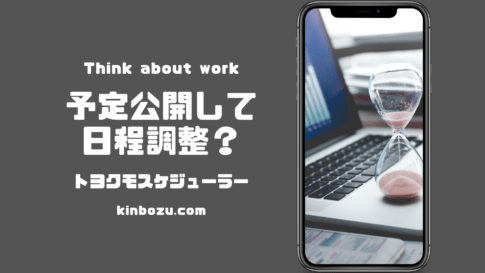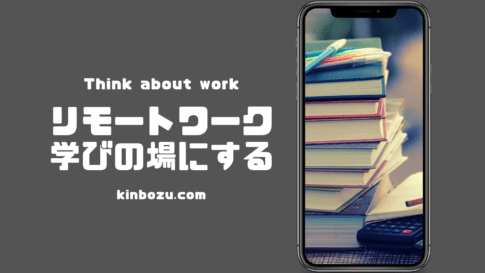前々職場には情報システム部門があって、パソコントラブルとかの対応はバッチリでした。
皆さんの職場には、パソコンやネットに詳しい方はいますか?
その人にいつも困ったら連絡している?
その人はそういったシステム関連を専門とする部署の方でしょうか?
前職は情報システム部門が存在せず、各々で対応する。難しければ外注するというスタンスでした。また、このような企業は周囲に多くありました。社内外に向けて、部門や担当は作るべきだと言い続けてきましたが、退職するまで実現することはなかったです。(退職後週1で自分が技術支援として契約を結ぶことになる) 退職note
社内の誰かがやってはくれない システム改善
まず、情報システム部門がないけど、困ったら助けてくれる人がいるって企業もあるでしょう。ただその人は自身の業務の合間に動いています。その人がいなくなったり、業務が忙しくて対応できなくなった時にその人を責めるのでしょうか?
そして、そういった人がいない企業の場合は我慢するなり、外注するなりで対応していると思います。誰かがやってくれるだろうではやってくれない。
低スペックのPCが仕事の邪魔でしかない
入職した時、メモリー2GBのPCが支給されました。顧客管理には、かなり作り込まれたExcelを使っていたので、Excelに情報入力するだけでフリーズする日々。
情報を入力する人は複数いて、入力された情報を集約して印刷して各部署に共有する日々。印刷したら帰れるけど、印刷前にフリーズ・・・
どうにかしたいという考えはあるものの、新しいPCをすぐに買ってもらえるわけもなく、何かツールを使って改善した経験もない。とりあえず魔改造されたExcelを修正していく。
Excelを修正しても、それが本当に正しいのかどうか分からない。
誰かに評価してもらいたくても、誰も判断できない。
進んでいる方向が正しいか分からない暗闇を歩いている状態でした。
現在コンサルティングをご依頼いただくようになりましたが、社内に判断できる人材がいないのであれば、一時的にでも外部に判断をする材料を提供してもらうことは重要。
判断できないから、決断できないって稟議を書いても保留されるケースもありました。
定時には帰れず、仕事は増えるという目処が見えない状態で、誰かに相談もできない状況は正直きつい日々でした。
業務改善で抑えておくべきポイント
色々と悩む中で、試行錯誤を繰り返しました(大体失敗)
そんな中で、自分の中でポイントとなった部分を書いてみます
先行事例はあくまで事例。そのまま導入は困難である。
何かを変えたいと思った時、先行事例は参考になります。
既に自分がやろうと考えていたことが実現していたり

と驚くケースも多々あります
先にチャレンジした先輩方の偉業は本当に参考になります。
ただ、先行事例はあくまで事例です。そのまま自分の環境に導入できるかどうかは分かりません。
- 導入までの背景が違う
- 企業全体の考え方が違う
- かけられるコストが違う
先行事例が成功しているから、そのまま自社でも同じようにと僕も思っていた時期がありました。先行事例と類似する部分を探す方が難しいくらい色々と異なる部分があります。
参考にすることはあっても、そのままは難しいというと無理でしょう。
先行事例はあくまで事例である。こういうことができるかもしれない。こういった手法を用いると効果的かもしれない。
かもしれないが、自分の環境ではどうだろうと考えてみるようにしましょう。
1人では無理だと立ち止まって考えよう
自分しか分からないから、自分がやるしかない
ツールの知識は自分しか分からないかもしれませんが、組織においてツールの知識だけが全てではありませんよね?
ツールを導入するにはコストがかかりますので、コストの承認が必要です。導入できたとしても、自分だけツールを利用する訳ではないでしょう。導入部署のメンバー、全社導入になるかもしれません。
そういった導入までの過程や、導入後のフォローを全て自分がやるのはかなり困難でしょう。特に専任の担当でないのあれば、早い段階で仲間づくりをしておきましょう。
仲間作りは別に社内のメンバーだけで作り必要はありません。外部から仲間を呼ぶことも大切です。私中々前に進めないって時は、外部からの後押しも効果的だと思います。
経営サイドのポイントは、環境を作る
自分ができないのであれば、人も簡単にはできない
何かを変えるには、タダでは変えることはできない。変えられるのであれば、既に変えています。
「頑張ってみろ」
「努力が足りない」
「考えたらよい」
そんな言葉では何も変わりません。言った方は満足かもしれませんが、どんな発言で変えられるものであれば誰も悩まない。明確な指示ができないのであれば、そこは現状では解決しない課題だと捉えましょう。
外部に委託するのか、現場が望むものにコストをかけるなど資金を投入する。どうしても投入したくないのであれば、その課題解決は諦めてください。
いずれ誰かが解決するだろう
待っていても解決する芽は生えてきません。もし解決した場合、奇跡が起きただけ。たまたま種が飛んできただけで、自分たちで育てた訳ではありません。しかし、そんな奇跡を自分たちが育てたと勘違いして、次の芽を期待している企業が多い気がします。
人材が育つには、育つ環境が必要です。自力で育つのを待つとしても、育ちやすい環境整備は必要だと思います。
情報システム部門が欲しかった訳ではないけど
育つ環境がなく、オンラインや業務改善の考え方も薄い。そこで、意識を変えるために勉強しました。自分が理解して、話せるようになればいずれ困った時に自分の知識が活かせる時がくる。
自宅でコツコツ勉強して、全然広がらない考え方やツールを3年程見守っていました。コロナ禍になり、オンラインって言葉が社内でよく出るようになりました。自分自身の需要も高まりましたが、結局情報システム部門の様な、専門的な部門はできず私は退職しました。
振り出しに戻らないよう、今までやってきたことが後退しないようにと話し合い、技術支援の契約をしました。外注先となった訳です。
支援のメインが教育で、いずれ完全に離れた時でも自立できる環境づくり。情報システム部門が欲しかった訳ではないですが、専任担当者は必要だと思います。一時的な外注で対応することはありだと思いますが、社内のことを理解した人間が担当として配置されることは企業のメリットが多いと思います。
よく「1人情シス」ってワードを聞きますが、これは怖いですよね。僕自身も兼任でしたが、1人でやっていた部分もあるので、退職時の穴は大きかったようです。ある程度教育をしてきたことで、全く対応できないって訳ではありませんが・・・
自然と業務改善は起きないし、ITリテラシーが高くなることもありません。そうなるにはきっかけが必要です。奇跡を待っているのではなく、動いてみましょう。
まずはどうするか・・・
セミナーに参加する前に、現場でミーティングしましょう。どんな課題を感じており、そのためにどう言ったことを取り組みたいのか。目の前のコストだけで判断しないでね